オーナーチェンジ物件は、「購入直後から家賃収入を得られる」「入居者募集の手間が省ける」といったメリットから、投資初心者にも人気のある選択肢です。一方で、「室内の確認ができない」「賃貸契約をそのまま引き継ぐ」など、見落としがちなリスクも存在します。
本記事では、オーナーチェンジ物件が"危険"とされる理由や、後悔を避けるための確認ポイント、購入の可否を見極める判断軸について解説します。
なお、ノムコム・プロでは会員登録者限定で「4つの特典」をご用意しており、不動産投資を始めたい方や保有物件の運用を見直したい方に役立つ情報やサポートを提供しています。最新の物件情報をいち早くチェックしたい方は、ぜひ下記リンクよりご登録ください。
※以下の情報は2025年8月時点の情報をもとに、宅地建物取引士の河原田琢人が監修しています。
この記事で分かること
- オーナーチェンジ物件は、入居者の情報や室内状況を把握しにくいといったリスクがある
- 投資判断には、契約内容や家賃設定などの細かい確認が欠かせない
- エリアの将来性や出口戦略を見据えて、長期的な視点で判断することが大切
目次
そもそもオーナーチェンジ物件とは?

不動産投資に関心を持つと、よく耳にするのが「オーナーチェンジ物件」という言葉です。
すでに入居者がいる物件が売買されるこの仕組みには、普通の中古物件とは違った特徴があります。この章では、オーナーチェンジ物件の基本的な意味や、他の物件との違いについて解説します。
1. オーナーチェンジ物件の意味と仕組み
2. 一般の中古物件との違い
オーナーチェンジ物件の意味と仕組み
オーナーチェンジ物件とは、入居者が住んだままの状態で売買される収益用不動産(一般には投資用不動産とも呼ばれる)のことです。新しいオーナーは、建物だけでなく「賃貸借契約」も引き継ぎます。
つまり、物件を買ったその日から家賃収入が発生しますが、同時に入居者の属性や契約内容を変更することは基本的にできません。入居者が優良で契約条件も妥当であれば安定収入が見込めますが、逆に家賃が相場より低かったり、契約期間が長すぎるケースもあります。
このように、オーナーチェンジ物件は「すぐに収益化できる反面、柔軟な対応ができない」という点が最大の特徴です。
一般の中古物件との違い
一般的な中古物件は空室の状態で売買されることが多く、買主は自分で住むこともできます。内見して状態を確認したり、自由にリフォームしたりできる点も大きなメリットです。
一方、オーナーチェンジ物件は入居者が住み続ける前提のため、室内を見られないことが多く、リフォームも入居者の退去後でなければできません。購入者は「住まい」ではなく「投資対象」として物件を評価する必要があります。
つまり、目的が「住む」か「稼ぐ」かによって、選ぶべき物件の種類が大きく変わってくるのです。
オーナーチェンジ物件の基本をさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:オーナーチェンジ物件とは?不動産投資初心者に人気の理由、注意点を解説!
オーナーチェンジ物件が危険と言われる7つの理由

オーナーチェンジ物件は、すでに入居者がいるという安心感から「投資初心者にもおすすめ」と言われることがあります。しかし、実際には見えにくいリスクも存在し、思わぬトラブルにつながるケースも少なくありません。
ここでは、なぜ「危険」と言われるのか、代表的な理由を具体的に見ていきましょう。
1. 入居者の情報を確認しにくい
2. 室内の状態を確認できない
3. 契約内容・家賃設定が引き継がれる
4. 悪質な入居者でも退去は簡単にできない
5. 住宅ローンの金利が高くなることがある
6. 建て替えやリノベーションが難しい
7. 購入後に物件の瑕疵が見つかることがある
理由1.入居者の情報を確認しにくい
オーナーチェンジ物件では、「すでに住んでいる入居者の個人情報」をどこまで開示するかが不動産会社によって判断されます。個人情報保護の観点で、購入前に具体的な個人を判断できる情報について開示をしないケースがあるのです。
| 事前の把握が困難な入居者の個人情報 | 氏名、勤務先、収入、家族構成、免許証、保険証など |
|---|---|
| 事前に把握できることもある入居者の個人情報 | 国籍、年齢、性別、勤務業種、居住歴、過去のトラブル滞納歴など |
職業、収入、家族構成、滞納歴などを把握できないまま購入を決めるケースも多く見られます。
そのため、問題のある入居者がいると気付かずに契約してしまい、後になって家賃の未払いが発覚するリスクもあります。また、トラブルを起こす住人がいれば、物件の印象が悪くなり、将来的な売却にも影響が出るおそれがあります。
見えないリスクを抱えるという点で、投資判断が難しくなるのが実情です。
理由2.室内の状態を確認できない
入居中の物件では、購入前に室内を確認できないことが一般的です。これは賃借人のプライバシー保護の観点から、内見が制限されるためです。結果として、築年数が古い場合などは、設備の老朽化や修繕が必要な箇所があっても気付けないおそれがあります。購入後に雨漏りや配管の不具合が見つかり、高額な修繕費が発生することも珍しくありません。
物件の状態を把握できないまま契約することが、将来のトラブルを招く原因になるのです。
理由3.契約内容・家賃設定が引き継がれる
オーナーチェンジ物件では、賃貸借契約がそのまま引き継がれます。つまり、新しいオーナーが自由に契約条件を変更したり、家賃を上げたりすることはできません。
例えば、現在の家賃が周辺相場よりも大きく下回っていた場合、収益性が低くなります。また、更新期間が長すぎたり、不利な特約が含まれていたりする契約内容もあります。契約を変更できないという制約が、経営の柔軟性を奪う要因になります。
また、家賃が周辺相場より高い場合についても注意が必要です。収益不動産は利回りで購入検討する投資家も少なくありません。それを逆手にとり、売却が前提であれば相場賃料よりも割高な賃料で入居者と賃貸借契約を交わし、高値で売り抜けようと考える投資家もいるので注意が必要です。
理由4.悪質な入居者でも退去は簡単にできない
入居者が問題を抱えている場合、退去を促すことは簡単ではありません。家賃滞納や近隣住民とのトラブルがあっても、法的な手続きを踏まなければ退去させることはできません。場合によっては、数ヵ月から1年以上かかるケースもあり、弁護士費用や裁判費用がかかることもあります。
オーナーが不利益を被る可能性があるため、購入前の情報収集が重要です。誰が住んでいるかを確認できないことが、大きなリスクになるのです。
空室が長引くと、投資家心理としても、入居者の属性にこだわらず早期に入居を決定させることを先行しがちになります。具体的な例としては、次のようなものが該当します。
1. 高年齢
2. 外国人
3. 敷金礼金ゼロ など
高年齢の場合は、入居者が亡くなるリスクが高まるため、敬遠されがちです。外国人の場合は、文化の違いによる室内破損、汚損、近隣トラブルなどのリスクから「外国籍NG」になっている物件も多くあります。敷金礼金ゼロの場合は、経済的に余力がなくても入居ができます。そのため、上記3点も受け入れられる物件だと、長期空室リスクを下げられる要因となります。
そのような投資物件を購入してしまった場合は、トラブルのリスクが格段に上がるので注意が必要です。
理由5.住宅ローンの金利が高くなることがある

オーナーチェンジ物件は「投資目的」と見なされるため、一般的な住宅ローンは利用できません。そのため、金利が高めのアパートローンや事業ローンを組む必要があります。
例えば、住宅ローンが年1%前後であるのに対し、アパートローンは2〜4%程度が相場です(※)。また、原則として変動金利でローンを組む形になるので、運用後も金利に変動があることも加味する必要があります。この差は返済総額に大きな影響を与えるため、想定以上の支出につながる場合があります。投資としての収支シミュレーションを厳密に実施しておくことが大切です。
※2025年8月現在
理由6.建て替えやリノベーションが難しい
入居者が住んでいる間は、大規模な工事や間取りの変更などに制限がかかります。特にファミリー物件や分譲マンションでは、リフォームの自由度が低いケースも少なくありません。
また、老朽化にともなう建て替えのタイミングも、入居者の退去状況に大きく左右されがちです。自由に手を加えられないことで、物件価値の回復や資産形成が難しくなる可能性もあります。
将来的にどの程度まで改修できるのか、購入前にしっかり確認しておくことが重要です。
理由7.購入後に物件の瑕疵が見つかることがある
室内確認ができない状態で購入するため、見えない部分に不具合が潜んでいることがあります。例えば、雨漏り・シロアリ・基礎のひび割れなどは、契約後に発覚することも少なくありません。
売主に責任を問える「契約不適合責任」の範囲や期間が短い場合、修繕費用をすべて負担する可能性もあります。契約時には、こうしたリスクに備えて条項の確認や保険加入も検討しましょう。
見えないコストを減らすには、事前の情報確認が何よりも重要です。
失敗しないために確認すべきポイント

オーナーチェンジ物件には独自のリスクがあるとはいえ、すべてが危険というわけではありません。実際、多くの投資家が安定した収益を得ているのも事実です。
大切なのは「どこを見るべきか」をあらかじめ知っておくこと。この章では、失敗を防ぐために確認すべき具体的なポイントを紹介します。
1. 売主の売却理由を把握する
2. 入居者の属性や滞納履歴を確認する
3. 家賃と周辺相場のバランスを確認する
4. 契約内容や管理状況を細かくチェックする
5. 物件周辺の環境を自分の目で確認する
ポイント1.売主の売却理由を把握する
まず注目したいのが、売主がなぜその物件を手放すのかという点です。売却理由には「資産整理」「買い替え」「相続」など前向きなケースもあれば、「空室が増えた」「入居者とトラブルがあった」など、リスクを手放すためのケースもあります。
もし売却理由が曖昧だったり、説明を避けられたりするようであれば注意が必要です。不安がある場合は、物件の稼働状況や過去のトラブル事例などを、不動産会社に確認しておきましょう。見えないリスクは、売主の本音にヒントが隠れていることもあります。ただ、不動産会社に確認をしても曖昧な回答が返ってくる可能性もあります。その場合は、ご自身で判断する力を身につける必要があります。購入をする前に、賃貸借契約書(属性の確認)、長期修繕計画(修繕費の値上げのタイミング)取得依頼をして確認するようにしましょう。重要事項調査報告書についても、マンションに借入がないかなどの確認ができます。
また、過去の空室期間なども、不動産会社に確認すれば情報を見ることができますので、依頼をするのも良いかと思います。
オーナーチェンジ物件が売却される理由について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
関連記事:オーナーチェンジ物件をなぜ売る?リスクと見極めポイントを徹底解説
ポイント2.入居者の属性や滞納履歴を確認する
現在の入居者がどのような人物かを知ることは、物件の安定運用に直結します。とはいえ個人情報保護の観点から、職業や年収といった詳細は開示されないケースが多いです。
その代わりに「レントロール」と呼ばれる書類には、入居期間や家賃の支払い履歴などが記載されている場合があります。特に家賃の滞納歴があるかどうかは、将来のリスクを見極めるうえで非常に重要です。
不安な場合は、管理会社や仲介業者にヒアリングして、できるだけ多くの情報を集めましょう。
ポイント3.家賃と周辺相場のバランスを確認する

物件がいくらで貸し出されているかだけでなく、周辺の家賃相場と比べて適正かどうかもチェックすべきポイントです。
相場より高すぎれば入居者が離れやすくなり、逆に安すぎると収益性が下がります。近隣の物件と比較することで、値付けの妥当性が見えてきます。ポータルサイトや国交省の家賃統計などを活用すると、相場感をつかみやすくなります。
契約後に家賃を大幅に見直すことは難しいため、購入前の段階での見極めが大切です。
ポイント4.契約内容や管理状況を細かくチェックする
オーナーチェンジ物件では、既存の賃貸借契約をそのまま引き継ぐのが原則です。そのため、契約内容に不利な条件が含まれていないかどうかを細かく確認しておく必要があります。
【具体的な確認ポイントの例】
● 契約期間
● 更新条件
● 敷金
● 原状回復の取り決め
また、物件の管理状態も要チェックです。修繕記録が残っているか、共用部分は清潔か、対応の早い管理会社かどうかも判断材料になります。長期運用を考えるなら、契約と管理の両面を丁寧に見ておきましょう。
建物の管理が自主管理となっている場合は、割安で物件が出ているケースも多くありますが、売却を検討した際に銀行が融資しづらくなる傾向があり、価格を大幅に下げないと売れないリスクがあります。
相場よりも安い物件を検討している場合は、なぜその物件が安いのかについて徹底的な調査をしたうえで購入の検討をしましょう。
ポイント5.物件周辺の環境を自分の目で確認する
駅までの距離やコンビニの有無だけではなく、治安や街の雰囲気なども重要な情報です。特にファミリー層や単身者など、入居者ターゲットが求める条件に合っているかを意識することが大切です。
現地を歩くことで、昼と夜の違いや、騒音・におい・人通りといったリアルな情報が得られます。物件自体が良くても、周辺環境に問題があると空室リスクは高まります。地図アプリやWebサービスだけに頼らず、現地で感じる「肌感覚」も投資判断に活かしましょう。
地図アプリやWebサービスの情報が最新の情報と異なっていることもよくあります。実際は、目の前に大きなビルやマンションが直近で建設されていたり、建設中であったりすることもあるので、ご自身の目でしっかりと現物を確認することをおすすめします。
オーナーチェンジ物件を購入すべきか迷ったときの判断軸
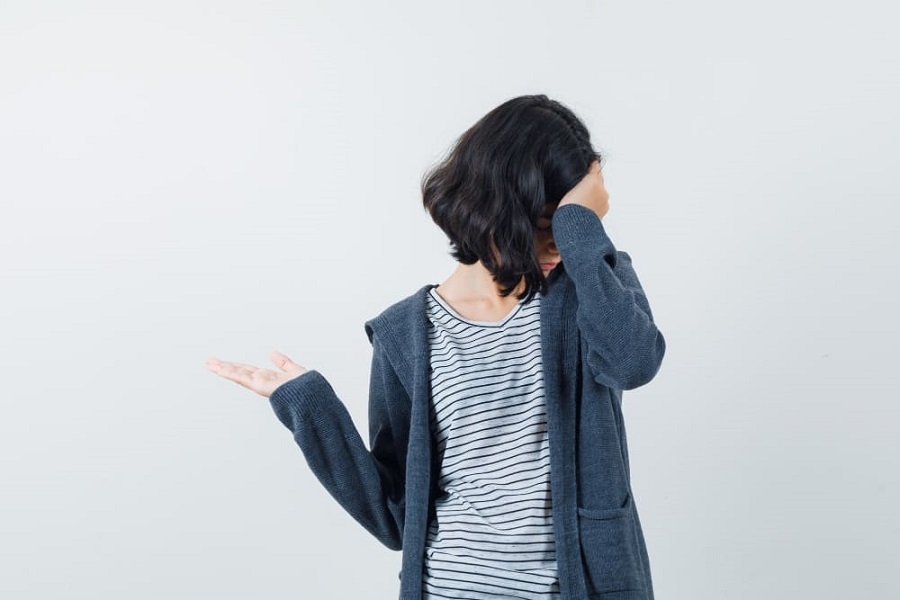
オーナーチェンジ物件を購入すべきか悩んだときは、いくつかの視点から冷静に判断することが大切です。最後に、購入を迷ったときに役立つ3つの判断軸をご紹介します。
1. 物件タイプやエリアの将来性を考える
2. 出口戦略(売却時)を想定しておく
3. 信頼できる不動産会社と相談する
物件タイプやエリアの将来性を考える
まず確認したいのが、物件の「間取り」と「立地」です。単身者向けのワンルームなのか、ファミリー向けの2LDK以上なのかで、入居者の需要は大きく変わります。
また、エリアの将来性も重要なポイントです。人口が増えている地域や再開発が進んでいる場所では、空室リスクを抑えやすくなります。逆に、人口減少エリアや交通の便が悪い場所は、長期的に入居者が見つかりにくくなる可能性があります。
「今の収益」だけではなく、「将来の安定性」を見据えた選択が求められます。
出口戦略(売却時)を想定しておく
不動産投資は買って終わりではありません。将来的に売却することも視野に入れて、「売れる物件かどうか」を考えておくことが大切です。築年数が古くなるほど売却価格は下がりますし、賃貸契約が継続していることで買い手が限られる場合もあります。
法人契約の社宅となっている場合は、長期にわたる契約になることが多く賃料の安定性は高いです。その一方で、賃料を増額したいと思ってもなかなか退去することが少なく、増額が難しいことも勘案しないといけません。売却する際にも、賃料が原因で思うような価格で売れないという結果になることもありますので注意が必要です。
また、相場より高く買ってしまうと、売るときに値崩れしてしまうこともあります。売却時に困らないよう、購入前から「出口戦略」を意識しておくと安心です。下記の記事では、不動産投資の出口戦略を目的別に解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:不動産投資は出口戦略で決まる!目的別「利益最大化のコツ」徹底解説
信頼できる不動産会社と相談する
初めてオーナーチェンジ物件を買う場合、自分ひとりで判断するのは難しいものです。そのため、実績のある不動産会社に相談することが、成功への近道になります。
大切なのは、物件の良い面だけではなく、リスクや注意点も正直に教えてくれるパートナーを選ぶことです。契約書のチェックや管理状況の調査など、専門的なサポートを受けることで、トラブルの予防にもつながります。
わからないことを気軽に相談できる信頼関係が、長期的な安心を生み出します。
下記の記事では、不動産投資の主な相談先と選び方を解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:不動産投資のおすすめ相談先6選!選び方や相談時に押さえるべきポイントを紹介
リスクを理解し、納得のいく投資判断をしよう

オーナーチェンジ物件は、すでに入居者がいるという特性上、一般的な中古物件とは異なるリスクとメリットをあわせ持っています。家賃収入がすぐに得られる一方で、契約内容の制約や物件状況の見えづらさといった課題にも向き合う必要があります。
「危険だからやめる」ではなく、なぜ危険とされるのかを理解し、正しく対処することが大切です。不安があれば信頼できる不動産会社に相談しながら、投資としての可能性を見極めていきましょう。
なお、ノムコム・プロでは会員登録者限定で「4つの特典」をご用意しており、不動産投資を始めたい方や保有物件の運用を見直したい方に役立つ情報やサポートを提供しています。最新の物件情報をいち早くチェックしたい方は、ぜひ下記リンクよりご登録ください。
よくある質問
Q:オーナーチェンジ物件は危険なのでしょうか?
A:一概に危険とは言い切れませんが、特有のリスクも存在するため、慎重な判断が必要です。リスクを理解したうえで正しく対処できれば、有効な投資手段になります。
Q:オーナーチェンジ物件が「危険」と言われることがあるのはなぜですか?
A:室内の状態を確認できない、入居者の情報を把握しづらいなど、見えづらいリスクが存在することが理由の一つです。
Q:オーナーチェンジ物件は危険なのでしょうか?
A:オーナーチェンジ物件で利益を出すことは可能です。物件選びや契約内容の確認、周辺相場との比較などをしっかり行えば、安定した家賃収入を得られるケースも多くあります。 また、売却益を狙う「キャピタルゲイン」なのか、安定収入を狙う「インカムゲイン」なのかによっても物件の選定ポイントは変わりますので、目的をしっかりと定めて投資商品を選んでいく必要があります。












