
マンション売却時は「いくらで売れるか」ということに目が行きがちですが、売却時に支払う手数料や諸費用を忘れてはいけません。費用感や支払時期は、売却するマンションのケースごとにさまざまですので、各費用項目について時間の経過を考慮して資金計画を立てておく必要があるでしょう。
この記事では、マンション売却時にかかるさまざまな費用や手続きについて、詳しく解説しています。手数料・諸費用の相場や計算方法を事前に把握しておけば、無駄な出費を抑えつつ、納得のいく価格で売却できるでしょう。
1.マンション売却時の手数料・諸費用の種類

マンション売却時の手数料には「必ずかかるもの」と「必要に応じてかかるもの」があります。どのような費用が発生するかは、住宅ローンの状況や売買契約時の契約条件によって変わるため、必要になる諸費用を資金計画の際に洗い出しておく必要があります。
1-1.マンション売却時の手数料・諸費用の相場
マンションを売却するときの手数料・諸費用合計の相場は、売却価格の3.5~4%といわれています。この相場はあくまでも目安のため、売却時に修繕やリノベーションによる追加費用がかかる場合は、この限りではありません。
1-2.マンション売却時の手数料・諸費用の種類
売却時にかかる手数料・諸費用は、不動産業者に支払うものだけではありません。金融機関への支払いや税金など、ほかにもさまざまな費用が必要です。こうした費用は、支払うタイミングも金額もバラバラのため、どのタイミングでどのような費用が発生するかを整理しながら把握しておきましょう。例えば、以下のような費用が必要です。
・(必ずかかるもの)仲介手数料・印紙税・引越し費用 ・(必要に応じてかかるもの)抵当権抹消費用・ローン事務手数料・クリーニング費用・譲渡所得税その他諸費用
1-3.売却時の手数料・諸費用一覧表
マンション売却時にかかる手数料・諸費用を、以下の表にまとめています。
| 項目 | 費用の目安 | 支払いのタイミング |
| 仲介手数料 | 原則として売買価格の3%+6万円(税別) | 契約時50%、引渡時50%が多い |
| 印紙税 | 売買金額によって異なる 1千万円超5千万円以下の場合1万円 |
契約時 |
| 抵当権抹消費用 | 2万円程度 | 住宅ローン完済時 |
| ローン事務手数料 | 3~5万円程度 | 住宅ローン完済時 |
| ハウスクリーニング費用 | 3.5~6万円程度。 マンションの大きさで異なる |
引渡前 |
| 譲渡所得税 | 譲渡益の39.63%または20.315% ※軽減税制あり |
売買の翌年の確定申告時 |
2.マンション売却時の仲介手数料

不動産売買における仲介手数料については「宅建業法」(宅地建物取引業法)で定められています。媒介契約は3種類(一般・専任・専属専任)ありますが、媒介契約の種類で手数料が変わることはありません。
2-1.仲介手数料の計算方法
不動産売買の仲介手数料は以下のように定められています。
| 成約価格 | 仲介手数料の上限(速算法) |
| 200万円以下 | 成約価格×5%(税別) |
| 200万円超~400万円以下 | (成約価格×4%)+2万円(税別) |
| 400万円超 | (成約価格×3%)+6万円(税別) |
宅建業法の条文では、200万円以下の部分について5%、200円超~400万円以下の部分について4%、400万円超の部分について3%と定められていますが、実務では上記の表のような速算表がよく使われています。プラス2万円、プラス6万円の部分は、手数料率の違いを調整したもので、実際に計算してみると、条文と速算表で同じ額の手数料が算出されます。
また、低廉な価格の不動産については、近年の空き家問題の解決を促進するため、令和6年7月1日施行の改正により「仲介手数料の特例」が定められました。この特例では、対象となる物件の価格を800万円以下に拡大し、上限となる報酬額を33万円(税込)としています。
2-2.仲介手数料の支払い方法
仲介手数料は、契約時50%、引渡時50%を不動産業者に支払うのが原則です。契約時は手付金が、引渡時には残金が支払いの原資となるため、手付金や残金の手取りが減ることを念頭に置いておきましょう。
3.仲介手数料無料の注意点

「不動産売買の仲介手数料を無料にします」と宣伝している不動産業者もありますが、良いことばかりではありません。不動産売買の仲介業務は、調査や交渉の手間や労力がかかるとともに、専門的知識が必要であるにもかかわらず、手数料が無料になっているのは不自然です。後々後悔しないためにも、無料と宣伝している裏にはなにがあるかを理解し、業者を厳選する必要があります。
3-1.熱心な売却サポートを受けられないことも
不動産業者の中には、起業し立てで売買実績に乏しく、顧客の獲得に苦労している業者も散見されます。こうした業者は、「仲介手数料は無料」として宣伝しつつ、実績を上げるため、「相場より安い価格で早急な売却を迫る」「短期間の売却活動を強いる」といったケースもあるようです。こうした状況で売却すると、仲介手数料が無料だとしても、結局手元に残る資金が少なくなるかもしれません。
3-2.囲い込みの罠
「囲い込み」とは、売却依頼を受けた物件を公開せず、業者が直接仲介できる買主のみに物件を紹介することを意味する業界用語です。通常、売却依頼を受けた物件が公開されると、買主側の仲介会社と取引する可能性があるため、売却依頼を受けた業者は買主から仲介手数料を受け取ることができません。直接仲介できる買主にだけ物件を紹介すれば、売主・買主両方から手数料を受け取れるため、「囲い込み」をする業者がいます。
不動産業者に囲い込みをされると、売却が遅れや価格交渉がスムーズに進まない事態になりかねません。売主にとって不利益となる「囲い込み」が発生しないよう、売り出し物件の公開や広告宣伝については、仲介会社から定期的に報告を受けておくことが大切です。
4.印紙税
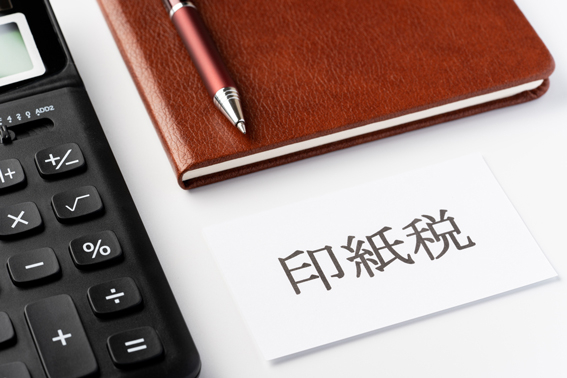
売買契約時は、「売買契約書」を取り交わします。売主・買主がそれぞれ「売買契約書の原本」を保有する場合、各々が「印紙税」を負担しなければなりません。もし、一方が原本を保有しており、もう一方が写し(コピー)を保有している場合は、「原本を保有する当事者のみ」が印紙税を負担します。
4-1.印紙税とは
「印紙税」とは、経済的な取引を証明する文書を作成した場合に課される税金で、収入印紙を文書に貼付することによって納税できます。高額な領収書が発行された際、店舗が印紙の貼りつけをするのは、領収書も経済的な取引を証明する文書(課税文書)のひとつと考えられているためです。不動産売買契約書も、印紙税が課される課税文書とされています。
4-2.印紙税額の一覧表
印紙税は文書に記載された契約金額によって税額が変わってきます。以下は、契約金額ごとに必要な印紙税の表です。なお、不動産の売買契約書については、印紙税の軽減の特例が適用されます。
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 1万円以下のもの | 非課税 |
| 1万円を超え10万円以下のもの | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 5千円 |
| 1,000万円を超え5000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
引用:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
5.抵当権抹消費用
住宅ローンを組む際、金融機関が担保として設定した抵当権は、売却時に抹消されていなければなりません。抵当権の抹消には、法務局に納める「登録免許税」に加え、司法書士に支払う報酬も必要です。なお、自分で抵当権の抹消手続きを行う場合、司法書士への報酬は必要ありません。
5-1.抵当権抹消費用とは
住宅ローンを完済すると、ローンの担保である抵当権は法的に消滅します。しかし、不動産登記簿上の抵当権の記載が自動的に更新されるわけではなく、抵当権の抹消には、登記手続きが必要です。登記事項の変更には「登録免許税」と「司法書士報酬」が必要になるため、このふたつを合わせて抵当権抹消費用といいます。
5-2.登録免許税
登録免許税とは、抵当権抹消登記を行うときに法務局に収める税金です。不動産の数ごとに1,000円の登録免許税がかかります。土地1筆と建物ならば、合計で2000円です。底地の登記がいくつかの筆に分かれている場合には、1筆ごとに1,000円が加算されます。マンションの場合は、敷地権が設定されている土地の筆数と建物で不動産の個数が決定されます。
5-3.司法書士報酬
抵当権抹消登記の申請書の書類作成から申請までを司法書士に委任することができます。司法書士報酬の相場はおおむね15,000円から20,000円程度です。
6.ローン事務手数料
売却時に住宅ローンの残債がある場合、売却時に住宅ローンを完済したあと、抵当権を抹消する必要があります。このとき、金融機関に住宅ローンの期限前支払い事務手数料として30,000~50,000円程度かかります。ローン事務手数料は金融機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
7.ハウスクリーニング費用
ハウスクリーニングは売主の義務ではありませんが、ハウスクリーニングをしておくと、部屋の印象が良くなり、検討客を増やすことが期待できます。築年数が古くリフォームが前提の物件ならば、あえてハウスクリーニングを行わないという選択肢もあるでしょう。
クリーニングの相場は、マンションでおおむね35,000~60,000円程度です。一戸建て住宅の場合、部屋数や広さによって、クリーニング料金に開きがありますので、事前にクリーニング業者から見積りを取っておくことをおすすめします。
8.引越し費用等その他諸費用
住まいを売却する際は、引越し費用のほか、不用品や廃棄物の撤去費用など、さまざまな費用がかさみます。一つひとつの費用はそれほど大きな負担ではないとしても、すべてを合計すれば無視できない金額になるため、諸費用はすべて見積りに入れておきましょう。
引越し先の住居購入のタイミングが合わないケースでは、仮住まいの住居費用が必要になるかもしれません。特に、売却する住宅に今も住んでいる場合は、仮住まいの住居費用も見込んでおく必要があるでしょう。
9.不動産の譲渡所得税
不動産の売却によって利益が見込めるなら、「譲渡所得の申告」が必要です。譲渡所得の申告は、給与所得や事業所得など、他の所得と合わせて確定申告を行います。給与収入しかない場合、確定申告の手続きはあまりなじみがないかもしれませんが、不動産の売買をした場合は、翌年の3月15日までに申告・納税しなければなりません(2025年に売却した場合、2026年3月15日まで)。
9-1.不動産の譲渡所得税とは
不動産の譲渡所得税とは、不動産の売却益にかかる所得税です。不動産の譲渡所得税は、給与所得や事業所得とは別に計算される必要がある「分離課税」であり、特別な税率が定められています。
売却益を計算する際に用いる、当初の取得費や譲渡費用には、計算方法や税率に詳細な規定があります。中には、相続で取得したもので取得費用が分からないこともあるかもしれません。このような場合には、税理士などの専門家に申告方法を相談しましょう。
9-2.譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけて計算するのが一般的です。計算方法は以下の通りです。
・譲渡所得=(売却価額)-(取得費+譲渡費用)
・譲渡所得税=譲渡所得×税率
上記の「取得費」とは、売買代金・不動産取得税・登記費用・測量費・造成費用など、不動産を取得するためにかかった費用全般のことです。また、この取得費は、購入代金から経過年数に応じた減価償却費を控除して計算します。相続や贈与、遺贈によって取得した不動産の場合、その被相続人や贈与者の取得費や取得時期を引き継ぐものとして計算されるのが一般的です。
9-3.譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、保有期間(短期か長期か)によって異なります。短期譲渡所得とは、「譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年以下の場合」です。基準となる日が譲渡日ではないことに注意してください。長期譲渡所得とは、「譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年を超える場合」です。
保有期間ごとの税率は以下の表の通りです。
| 短期譲渡所得の税率 | 39.63%(住民税・復興特別所得税含む) |
| 長期譲渡所得の税率 | 20.315%(住民税・復興特別所得税含む) |
9-4.譲渡所得税の特別控除や軽減税率の特例
譲渡所得税には、さまざまな特別控除や軽減税率の特例があります。特に、自宅を売却するときには、譲渡所得税の負担は大幅に軽減される特別税制があるため、ぜひ活用していきましょう。
まず、マイホーム(自宅のことをこのように表現します)を売却したときには、所有期間を問わず、譲渡所得から上限3000万円の特別控除を受けることができます。さらに、所有期間が10年を超える場合には、6000万円以下の部分について、計14.21%の軽減税率が適用されます。
また、所定の条件を満たせば、マイホームの買い替え時に得る剰余所所得を、新しい住居を売却するときまで、繰り延べておくことも可能です。反対に、譲渡所得ではなく譲渡損失が生じたときは、ほかの給与所得や事業所得と損益通算できる上、さらに3年間の繰越控除も可能になります。
10.いくら残る?マンション売却時の費用シミュレーション

以下の売買条件において、手元にいくら残るかをシミュレーションしてみましょう。
【売買条件】
住宅の種類 鉄骨鉄筋コンクリート マンション
売却価額 4500万円(取得費3500万円、うち土地2000万円・減価償却後建物価格1500万円)
保有期間 13年
抵当権抹消費用 52,000円(税込)
ローン事務手数料 50,000円(税込)
ハウスクリーニング費用・引越し費用その他諸費用80万円(税込)
【仲介手数料】
(4,500万円×3%+6万円)×1.1(消費税)=1,551,000円
【印紙税】
10,000円
【譲渡所得税】
・譲渡費用
1,551,000円+10,000円=1,561,000円
・譲渡所得税
{4500万円-(3500万円+1,561,000円)}×14.21%=1,199,182円
【手残り額】
4500万円-(1,551,000円+10,000円+52,000円+50,000円+800,000円+1,199,182円)
=41,337,818円
11.マンション売却時に精算・返金されるもの
支払済みの費用の中には、マンション売却時に精算・返金されるものがあります。契約時に精算金の漏れがないか確認するとともに、保険会社や金融機関に支払金額の内容を確認し、確実に返金手続きをしていきましょう。
11-1.固定資産税・都市計画税の精算金
すでに支払った当年分の固定資産税・都市計画税については、引渡日を基準日として固都税の精算を行います。精算金の明細については、仲介会社に作成を依頼しましょう。
11-2.管理費・修繕積立金・施設利用料等の精算金
年額・月額で支払う管理費・修繕積立金・施設利用料も、売主買主間で精算の対象となりますので、引渡日を基準に精算します。一方、過去に収めた管理費や修繕積立金については、管理組合から償還されることはありません。
11-3.火災保険料
火災保険を長期一括払いしている場合には、残年度の保険料が返金されます。売却前に、損害保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。
11-4.住宅ローンの保証金
住宅ローンの保証料を外枠で一括払いしている場合には、繰上げ一括返済によって保証料が返金される場合があります。ただし、住宅ローンの保証金については、金利に上乗せされて支払うケース(内枠方式)と、一括で前払いするケースが存在するため、支払いパターンが分からないときは、金融機関に確認してみてください。
12.まとめ
マンション売却時には、仲介手数料以外にもさまざまな手数料・諸費用が必要です。支払時期も、契約前、契約時、引渡時、確定申告時など、項目によってタイミングが異なるため、資金計画を立てる際は、どの手数料を、いつ支払うかについて整理しておく必要があるでしょう。
中でも、譲渡所得税については計算や特例の適用が複雑になりがちです。取得費や譲渡費用の算出について不安がある場合には、税理士をはじめとする専門家に相談するのが良いでしょう。

宅地建物取引士
株式会社イーアライアンス代表取締役社長。中央大学法学部を卒業後、戸建・アパート・マンション・投資用不動産の売買や、不動産ファンドの販売・運用を手掛ける。アメリカやフランスの海外不動産についても販売仲介業務の経験をもち、現在は投資ファンドのマネジメントなども行っている。
あわせて読みたいコラム5選
不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!


新着記事
-

2025/11/19
土地の売買で気をつけることは?売買契約におけるマナーや失敗例を紹介
-

2025/11/19
築50年一戸建ての売却相場は?かかる税金や解体費用も解説
-

2025/11/19
家が売れない時代なのは本当?1年以上売れない家の特徴と対策
-

2025/11/05
中古マンションの購入にかかる税金とは?
-

2025/11/05
中古の家を高く売るベストタイミングの最適解と見極め方法を紹介【2025年最新版】
-

2025/11/05
35年ローンの途中で売るときの注意点は?売却手順と完済できないときの対策
人気記事ベスト5
不動産売却ガイド
- 最初にチェック
- 不動産の知識・ノウハウ
- 売却サポート
- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス
- お買いかえについて
- お困りのときに
カンタン60秒入力!
売却をお考えなら、まずは無料査定から
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ















