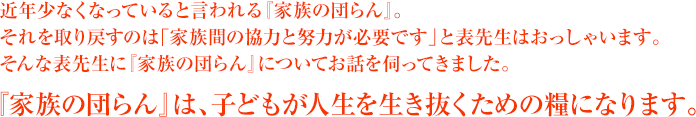京都女子大学発達教育学部教授 表真美 さん
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(学術)。専門は家族関係学、家庭科教育学。主な著書・論文に『現代家族のアジェンダ』(世界思想社、共著)、『少子化社会の家族と福祉』(ミネルヴァ書房、共著)、『小学校家庭科指導の研究』(建帛者、共著)、「明治期婦人雑誌・総合雑誌における「食卓での家族団らん」」『日本家政学会誌』2006年、「大正・昭和前期の家事科教科書における「食卓での家族団らん」」『日本家政学会誌』2007年他、多数。

そもそも私たちの暮らしのベースは一体どこからきているのでしょうか。
「それは大正期の俸給生活者と言って、今でいうサラリーマン家族の暮らし方からきています。地方独自の文化の中で作られていたのですが、高度経済成長期のテレビの普及によって地方の情報を共有しだしてから、またどんどん変わっていきました。というか、似てきたのかな」
団らんは昔からあったんですか。
「団らんそのものは昔から受け継がれてきた伝統ではありません。特に明治期は一般の人は貧しいですから、食事をゆっくり食べるという余裕もない。ましてや夕食の時間など、明るい場所もないし、部屋もない。子供は奉公に行ったり、家制度の中で、男が先に食べて女は土間で食べるとか、本当に状況は様々なんですけど、集まって食べることは難しかった。囲炉裏の周りに集まったとしても食べ物は貧しいモノ。ただ階級の高い人は別ですよ。使用人が食事の準備をして、階級の高い家族はそれを待って、みんなで食べるような。そういう中でテレビが普及する戦前までは政府の教育が基本となり、食事中はしゃべってはいけないという『しつけ』をもとにした『静かに食べる団らん』が実現していきました」
テレビの普及と家族の団らんの相互関係が気になります。
「ホームドラマの中に食事シーンが当たり前に、でてきたことです。しかも和気あいあいとおしゃべりをしながら食事をするという。社会学者で飯食いドラマと呼ぶ人もいるくらいです。そこからですね、『団らん=食卓』という考えが根付いていったのは」
でも表先生は『団らん』は食事だけにこだわることはないといいます。「一緒に食事をすることと『団らん』は、同じようで違います。『団らん』の方法は他にもあって、一緒に走ったり、散歩したり、趣味を共有することも『団らん』です」とおっしゃいます。
では、『団らん』に必要なものは何なのでしょうか。
「『時間』と『空間』、そして、それを支える主婦です。『団らん』は舞台のようなもの。その舞台監督が主婦なんです」と。しかしその一方で「今は女性も働かなくちゃいけないから、主婦の時間的余裕がなくなってきてます。だからこそ、すべてを舞台監督の主婦一人に押し付けるのではなく、自分の優先することを少し置き、家族みんなが協力して団らんを作る努力をしなといけない」と表先生は強調されます。

そこで、団らんを取り戻す方法としてあげられたのが家庭科教科書の中に記されている「団らんを工夫しましょう」でした。「家族の時間がバラバラで集まるのが難しいなら、せめて朝だけでも早起きして集まりましょう、土曜日は集まるようにしましょう、など家族で工夫をして、家族と一緒の時間を持つことが大切なんです。普段からまとまりのある家族はご飯も一緒に食べているし、ご飯を一緒に食べている家族はまとまりがあります。私は朝マックでも、みんなが一緒に食べるのならいいと思っています」。
表先生が実践する家族の団らんは…
では表先生ご自身はどういう工夫をされているのでしょうか。
「まずリビングが散らかっていません。家族のだれもが、すぐ座れるようにしています。床暖も取り入れています。うちはみんなでマグロのように寝転びながらテレビを見て、あったかいね、と楽しんでいます。家の間取りも、リビングを通らないと子供部屋のある2階に行けないようにしました。子供の顔はいつも見れるし、どういう友達が来ているのかも分かります」というように、表先生の舞台監督としての工夫は、家の作りにまで及んでいます。「幸い、私は食事を作るのも食べるのも大好きだから、子供たちも好きになってくれました。私の朝はパンと珈琲ですが、私の横で子供は自分でごはんと前の日の残りものをチンして食べてます。もう大きくなりましたから」
最後に先生が考える『家族の団らん』とは、をお聞きしました。
「家族の思い出作りかもしれませんね。親にとってはその思い出が人生の充実を育んでくれます」。では子供にとってはどうなのでしょうか。「その子が人生を生き抜く時の糧になります。人生にはいろんなことが起こります。それを乗り越える時のエネルギーになってくれるんです」。『家族の団らん』にこだわり、研究し続けて30年。先生の笑顔には、みんなのしあわせを願う教授としての深い愛情が満ち溢れていました。
私のお気に入り時間 - バックナンバー
- 花のある暮らし
- 工作気分でDIYチャレンジ!
- 始めよう!レモンライフ!
- 食卓がにぎわう産地直送
- 心と体を整えるおうちdeヨガ
- 今日から実践、楽ラク節約術!
- 春の野菜を食べよう
- しあわせキッチン
- 冬の乾燥対策!
- おうち和ごはん。
- 思い出を整理しよう
- おうちで家族団らんしよ。
- 模様替えがもたらす不思議な力
- 月を楽しもう!
- ぐっすり眠る知恵
- 麦茶をおいしく作るコツ
- 梅の力を知ろう
- 二度と散らからない収納術
- ベランダで家庭菜園にチャレンジ!
- おうちカフェしよう
- 一番フィットする靴下を探そう
- 美味しいごはんを食べよう!
- 風水おそうじ大作戦
- 至福のお風呂タイム
- パジャマをもっと見直そう
- あかりがもたらす豊かさ
- ござのなごみ