はじめに、用具の準備をしておこう
梅仕事は強力な酸を伴います。金属素材の道具の使用はさけ、ガラス、ホーロー、陶器製のものを使用しましょう。次に大きめの保存容器を用意。熱湯消毒をして、水気を完全に乾かします。さらに、焼酎で殺菌すれば完璧です。用意するものはこれだけなのです。

梅の種類は南高、白加賀、古城、養老など約300種あるといわれています。その中で梅干に最適なのが南高梅。梅干しの代表格ともいえる存在です。知るよりもまずは実践!6月中旬~下旬が梅干しづくりの旬の時期。実際に梅干しを作ってみましょう!
梅仕事は強力な酸を伴います。金属素材の道具の使用はさけ、ガラス、ホーロー、陶器製のものを使用しましょう。次に大きめの保存容器を用意。熱湯消毒をして、水気を完全に乾かします。さらに、焼酎で殺菌すれば完璧です。用意するものはこれだけなのです。


作る人や梅の種類によって、微妙に味が違うと言われる梅干。自分のオリジナルの梅干しが作れたら、毎日の食事がもっと楽しくなるはず。6月中旬からが梅干しの作りどきです。健康のために、家族のために梅干しを作ってみませんか?







工程の中で出てくる梅酢。いろんな使い方ができます。

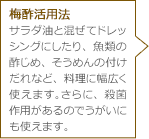









 江戸時代に記された「雑兵(ぞうひょう)物語」には、いくさに明け暮れる武士が梅干しを携帯していたと書かれています。古くから梅干は保存食として重宝されてきたことがわかりますね。
江戸時代に記された「雑兵(ぞうひょう)物語」には、いくさに明け暮れる武士が梅干しを携帯していたと書かれています。古くから梅干は保存食として重宝されてきたことがわかりますね。
ひとくちに梅干しといえども、漬け方にもさまざまな種類があります。食べ比べてみると、同じ梅でも味も香りも変わります。出来上がった梅干しを前に、いろんな漬け方も試してみましょう!




参考:梅干博覧会より