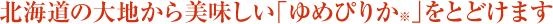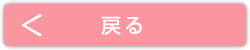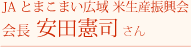
- 北海道の中でも良質の米が穫れることで有名な厚真(あつま)町。120年続く農家の4代目として11ヘクタールの土地を父から継ぐ。気付いたら父の手伝いをしていた安田さん。黙々と農作業をする父の背中を見て「米作りに妥協はない」と教えられたそうです。
「やっとここまできました」。北海道の胆振(いぶり)・日高地区で良質の米作りを推進する会長としての使命を持つ安田さん。最近のゆめぴりかの躍進は安堵に近いものがあるといいます。
「北海道米はずっと『やっかい道米』といわれて不味いというイメージがつきまとっていました。苦しかったですね。作っても作っても、業務米にしかならなくて、消費者の方においしいお米を届けたいという想いをずっと引きずっていました」。安田さんだけに限らず、北海道全域の生産者の苦闘は実に長く続きました。
というのも、気温の低い北海道の米はアミロース(でんぷんのこと。低いほどお米は粘ります)が高くなるために「硬い米」という印象があったそうです。
一新したのが今や人気米の上位に位置する『きらら397』(1990年)や『ななつぼし』(2001年)が出てからです。それでも『コシヒカリ』や『あきたこまち』などの人気米と並ぶことはできませんでした。「何とかしないといけない」という強い思いは安田さんたちのような生産者だけでなく、北海道内の研究者・販売担当など農業関係者すべてに「鬼気迫るもの」があったといいます。
「道内生産者みんなの想いを一身に背負った『ゆめぴりか』の誕生でした」。2009年のことです。
生産者だけでなく、研究者の努力の集大成とも言われる『ゆめぴりか』ですが、誕生秘話の物語ができるほど難産だったようです。
味はよくても収量が目標値に届かず、研究の途中でお蔵入りをした品種でした。数奇な運命にさらされながらも誕生へこぎつけたのは、何度も繰り返される食味試験で、その美味しさを示し続けた結果です。
特Aに該当する北海道米は「これしかない」。研究者の熱い想いを引き継いだ生産者たちの奮闘努力の結果、2011年には「日本穀物検定協会」の米食味ランキング最上位の「特A」を獲得。北海道から発信される美味しいお米に成長しています。
こうした生産者たちの「良食味米を作りたい」という想いは、自らに課した高いハードルからも理解できます。
「美味しさを守るために、生産者を組織化して統一した基準を設けたんです。毎年必ず専用のタネからつくること。お米の特性が十分に発揮されるようにふさわしい環境で育てること。質の高い味わいを保てるようにタンパク値を基準値以下(精米タンパク7.4%以下)に抑えること。それらをクリアーしたお米だけが『ゆめぴりか』として認定され、販売してもらえるんです」と安田さん。
しかも、すべての生産者が専用のタネをもらえるわけではなく「今までの生産実績、また量より質を追求できる農家だけに限定されます。もちろん収入が減ることは覚悟の上です」。
それは、農家の4代目として実直に田んぼを耕し次の世代に引き継いでいかないといけないという、安田さんが自らに課した「責務」でもあります。「私が先頭きってがんばらないとですね」。雪の降る大地の上で真一文字にかみ締める口元から揺るぎない覚悟を感じました。
『ゆめぴりか』の美味しさとは?「ほどよい粘りと豊かな甘みがあります。形状はやや大きめで細長く、食べたときの食感は、粒立ちがはっきりしていて、もちっとした食べ応えがあります」と安田さん。

美味しいお米作りに欠かせない寒暖の差は、日本のどこよりも激しい北海道。開花するまでの暖かい時期は、水管理や病気対策に追われます。秋がきて、黄金色にそまるたわわに実った稲の刈り入れ時期には刈遅れしないように日の出から田んぼに出ることも。
「美味しいお米を作るために、雪が積もる時期以外、ずっと走っています」とぼそっとつぶやくように語る安田さんの横顔は、極寒の地・北海道の大地を耕す生産者としての誇りに満ちていました。
私のお気に入り時間 - バックナンバー
- 花のある暮らし
- 工作気分でDIYチャレンジ!
- 始めよう!レモンライフ!
- 食卓がにぎわう産地直送
- 心と体を整えるおうちdeヨガ
- 今日から実践、楽ラク節約術!
- 春の野菜を食べよう
- しあわせキッチン
- 冬の乾燥対策!
- おうち和ごはん。
- 思い出を整理しよう
- おうちで家族団らんしよ。
- 模様替えがもたらす不思議な力
- 月を楽しもう!
- ぐっすり眠る知恵
- 麦茶をおいしく作るコツ
- 梅の力を知ろう
- 二度と散らからない収納術
- ベランダで家庭菜園にチャレンジ!
- おうちカフェしよう
- 一番フィットする靴下を探そう
- 美味しいごはんを食べよう!
- 風水おそうじ大作戦
- 至福のお風呂タイム
- パジャマをもっと見直そう
- あかりがもたらす豊かさ
- ござのなごみ