第2話頭金を上手に貯めるには?
夢のマイホーム・オーナー目指し、日夜、情報収集に余念のない野村夫妻。
そんな折、「頭金っていくら必要?」という話題になったのですが、なんと、健太には貯蓄がほとんどないことが発覚。理想的な自己資金は諸費用分も考えると物件価格の約30%といわれるだけに、野村夫妻のマイホームの夢は早くも暗礁に乗り上げてしまうことになるのでしょうか……。

- ねえねえ、今度の休日、○△駅前にできるマンションのモデルルームに行ってみない?
- いいけど、○△駅前っていったら、一等地だから高いんじゃないの?
- うーん、そうなのよねぇ。頭金をちょっと多めにすれば、手の届かない値段じゃないと思うんだけどなあ……。
- まあ、見るだけならタダだから、いいよ(笑) ところで頭金って、いくらぐらい用意すればいいのかな?
- 普通は、物件価格の20%ぐらいは用意するっていうわね。
- ということは、4,000万円の物件なら800万円くらいは必要ってこと!? うへえー。
- 新居に引っ越ししたら新しい家具だって揃えたいし、頭金が多いほどローンの負担が少なくなるわけだから、できればもっとたくさん用意したいわねえ。
- うーむ……。
- ねえ、ケンくんは、いまいくら貯金あるの?
- (通帳をじーっと見つめて)ええと……10万円くらいかな。
- それは貯金って言わないんじゃない?(笑)
- ……すいません。
- まあ、仕方がないわね。そんなことだろうと思って、私がちゃんと貯蓄をしておきましたから。
- さすが美咲ちゃん! いくらぐらいあるの?
- そうねぇ、定期預金とかも合わせると、500万円くらいかしら。
- ご、ごひゃくマンエン!? いつの間にそんなたくさん貯めてたの!?
- 結婚する前から財形貯蓄とかをやってコツコツ貯めていたのよ。
- ザイケイチョチク?
- もう、ほんとになにも知らないのね! 「財形住宅貯蓄」というのが正しい名前なんだけど、会社で毎月もらうお給料から好きな額を貯蓄に回していくシステムのことなのよ。
- へえー、そんなシステムがあるんだ!?
- このシステムのいいところはね、お給料から天引きされるから、毎月きちんと貯蓄ができるところ。ケンくんみたいに、なかなかお金が貯まらないという人にはぴったりなシステムじゃないかしら(笑)
- わかったってば、もう……。
- それから、普通の定期預金なんかだと利息から20%の税金が引かれちゃうんだけど、財形住宅貯蓄の場合は、元利合計で550万円まで利子が非課税なの。1円でも多く住宅資金にしたいという人には結構大きいと思うわ。他にも、財形貯蓄にはいろいろとメリットがあるのよ。
ファイナンシャル・プランナー's アドバイス!
なかなか貯まらない!という人にオススメの「財形住宅貯蓄」
住宅購入の際には、頭金以外にも、住宅ローン手数料、登記費用、不動産取得税などの諸費用が必要です。また、仲介物件の場合は、仲介手数料もかかります。諸費用として約5%~8%、頭金を20%とすると合計で物件価格の約30%程度の現金を用意するのが理想的です。頭金の準備は数年前から計画的に行い、少しでも住宅ローンの負担を減らすようにしましょう。
まだいつマイホームを買うかわからないという方や、なかなか思うように貯蓄ができない、という方には、給与から天引きしてくれる「財形住宅貯蓄」の利用がオススメです。「財形住宅貯蓄」のメリットは、元利合計550万円まで利子非課税、1年以上積み立てを続け残高が50万円以上ある場合は「財形住宅融資」を受けることもできるといった点です。なお、「財形住宅貯蓄制度」は、住宅の取得・増改築以外の目的で引き出すと、非課税などの優遇が受けられなくなるので注意してください。
「財形住宅貯蓄」の利用は、勤務先で制度を採用している場合に限られます。もし勤務先で「財形住宅貯蓄制度」を扱っていないという場合は、銀行の「自動積立定期預金」等、預貯金口座から自動引き落としで積み立てを行える貯蓄システムを活用しましょう。
表1 なかなか貯まらない!という人にオススメの「財形住宅貯蓄」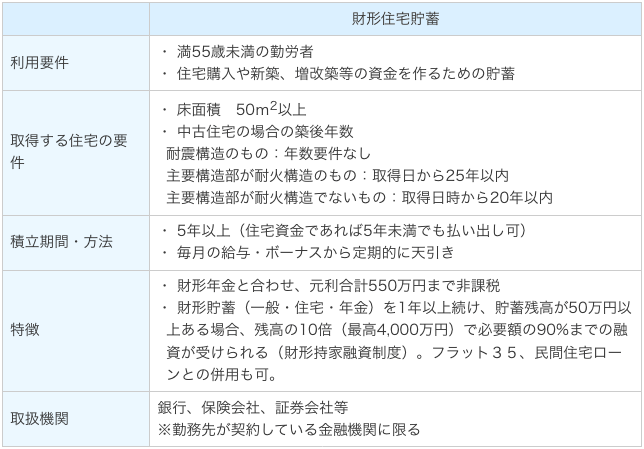
- よし、じゃあ、美咲ちゃんの500万円を頭金にして、僕がもう少しがんばって節約して――
- あら、ダメよ。貯蓄を全部使っちゃったら、急にお金が必要にあったときに困っちゃうでしょ?
- あ、そうか。じゃあ、いくらかは残しておくと……でも、そうすると頭金の目標額にぜんぜん届かなくなっちゃうんじゃ……。
- 足りない分も住宅ローンで用意するという手もあるんだけど、私たちの返済能力を考えたら、やっぱり現金できちんと用意したほうがいいと思うわ。ここはやっぱり、ケンくんにもっともっとがんばって働いてもらうのが一番ね(笑)
- ええ、もっと働けって……!?
- 冗談よ~(笑) マジメな話、お互いの親に援助してもらうという選択肢もあるわ。
- ホッ(笑)じゃあ僕は貯金がない分、そっちの交渉でがんばってみるか(笑)
- 期待してるわよ(笑) でも、両親からお金をもらうと贈与税がかかるのよ。
- ええ、家族同士なのに税金がかかるの?
- そうなのよ。でも、安心して! 住宅資金としてもらう場合なら、贈与税がかからないうれしい制度があるの。「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」や「相続時精算課税制度」って言うものよ。
- へぇ~、名前はややこしいけど、ありがたい制度だね。おやじに援助を頼んでみようかな。
- マイホームを手に入れるまでには、まだまだいろんなハードルがあるのよ。でもそういう苦労をたくさん乗り越えて手に入れたマイホームは、喜びもひとしおだと思わない?
- そうだね! よーし、なんだかやる気が出てきたぞ! 僕もがんばって貯蓄を始めてみるかな。
- もうちょっと早く始めてくれたらよかったのにねえ(笑) でも、繰上返済もできるから、今からスタートしても遅くないわね。ついでに、飲みに行く回数をもっと減らしたら?(笑)
- 了解です……。
ファイナンシャル・プランナー's アドバイス!
親からの資金を援助してもらう場合は特例制度を利用しよう!
両親に住宅購入のための資金援助をしてもらうケースもあるでしょう。通常は、まとまった額の贈与を受けると贈与税がかかりますが、住宅を取得するための贈与については、一定額までは贈与税がかからない制度が2つあります。1つは、「住宅取得等資金の非課税制度」、もう1つは「相続時精算課税選択の特例」です。
1 「住宅取得等資金の非課税制度」
20歳以上の人が、父母や祖父母などから住宅資金等の贈与を受けた場合、一定額までは贈与税がかからない特例制度です。非課税枠は、契約締結日、住宅の種類、かかった消費税率によって表2のとおりとなります。
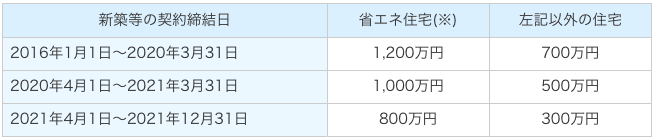 消費税が10%である場合
消費税が10%である場合
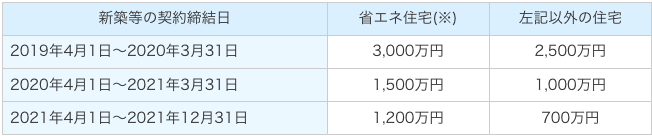
- 省エネ住宅:断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上、又は耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物、又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である住宅用の家屋
2 「相続時精算課税選択の特例」
20歳以上の人が、父母または祖父母から、住宅資金等の贈与を受けた場合、特別控除額の2,500万円までは、贈与税がかからないという制度です。2,500万円を超える場合は、超えた金額に対して、税率20%で贈与税がかかります。ただし、贈与を受けた額は、贈与した父母や祖父母が亡くなった時の相続財産に合算されます。贈与税はかからなくても、将来、相続税がかかるケースもあるため、税理士などに相談したうえで利用を検討してください。
これら2つの制度は併用もできます。多額の援助を受ける場合は、住宅取得等資金贈与の非課税制度、相続時精算課税制度の順で、利用を考えていくとよいでしょう。
表3 住宅資金等の贈与が非課税になる2つの制度 (平成33年12月31日まで)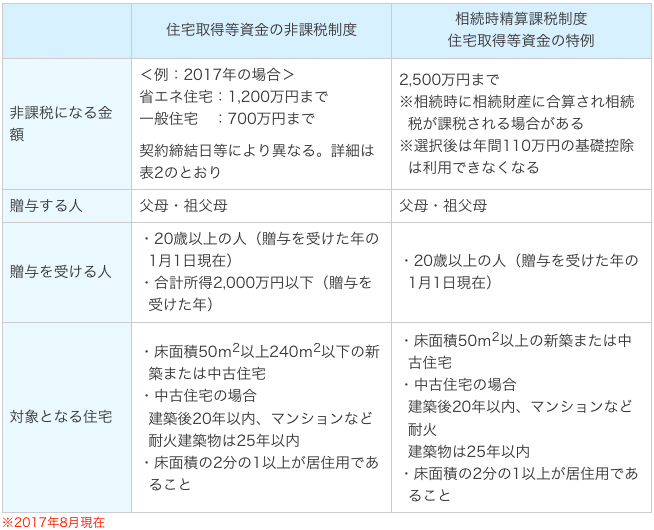 ※2017年8月現在
※2017年8月現在
なお、これらの制度を利用した場合には、贈与税の確定申告も必要です。利用を考える人は、国税庁のホームページや最寄りの税務署などで、あらかじめ詳細を確認するようにしてください。
今回の教訓
貯蓄は苦手!という人は、財形住宅貯蓄などを活用して着実に積み上げよう!
親からの資金を援助してもらう場合は、特例をチェック!
- バックナンバー
- 第1話 住宅ローンはいくらまで借りられる?
- 第2話 頭金を上手に貯めるには?
- 第3話 銀行ローンとは違う?「フラット35」ってどんな住宅ローン?
- 第4話 固定?変動?それとも両方?金利タイプはどれを選べばいいの?
- 第5話 一文字違いでも大違い!?元利均等返済と元金均等返済お得なのはどっち?
- 第6話 購入決定!諸費用ってどれくらいかかるの?
- 第7話 備えあれば憂いなし!マイホームオーナーに必要な保険とは?
- 第8話 繰上返済はいつするべき?
- 第9話 入居10年目、そろそろリフォームしたい!でも費用は?
- 住宅ローンの選び方・基礎知識・金利情報など
- 住宅ローンコラム
- 自分にあった住宅ローンを選ぼう
- 生涯賃金から選ぶライフプランシミュレーション
- 健太と美咲の住宅ローン奮闘記