建築
古民家・町屋リノベーションによる地方創生 第1回 ~ケーススタディ~

現在の日本において、地方の活力低下は喫緊の課題であり、人口減少と高齢化が進行する中で、全国各地で空き家問題が深刻化しています。特に、その地域固有の歴史や文化を色濃く反映する町屋や古民家といった伝統建築の空き家は、単なる遊休資産にとどまらず、放置すれば景観の悪化や防犯・防災上のリスクを増大させる要因となりかねません。
しかし、これらの町屋や古民家は、適切にリノベーションを施すことで、その地域の新たな魅力として生まれ変わる大きな可能性を秘めています。リノベーションとは、単に古くなった部分を修復するだけでなく、既存の建物をより良く、より快適に、より価値のあるものにするための改修をいいます。伝統建築を現代のニーズに合わせて再生することは、単に建物を修繕する以上の価値を生み出します。それは、地域経済の活性化に繋がり、新たな住民の移住・定住促進し、地域コミュニティを再構築するきっかけとなります。
中でも注目すべきは、リノベーションされた町屋や古民家が、訪日外国人観光客(インバウンド)誘致の強力なコンテンツとなっている点です。日本の伝統的な暮らしや美意識を体験できるこれらの施設は、高まるインバウンド需要に応え、地域に新たな経済的恩恵をもたらしています。
本レポート第1回では、古民家・町屋リノベーションが地方創生にどのように貢献しているのか、具体的な成功事例を詳細に分析します。特に、その経済効果、インバウンド誘致への貢献、そして事業を担った企業や地域の取り組みに焦点を当てます。
【サマリー】
- 古民家のリノベーションは、日本の地方が持つ多様な歴史・文化的な魅力を現代に蘇らせ、地方創生とインバウンド誘致の強力な原動力となり得るものです。本レポートで分析した成功事例が示すように、古建築が持つ唯一無二の価値は、訪日外国人観光客に特別な体験を提供し、地域経済に大きな恩恵をもたらしています。彼らは単なる宿泊施設を求めるのではなく、その土地ならではの文化、歴史、そして人との交流を求めており、古民家・町屋はそのニーズにまさに合致しています。
- 古民家・町屋のリノベーションを成功させるポイントはいくつかあります。第一に、その建物が持つ歴史的・文化的価値を最大限に活かし、地域固有の魅力を引き出すコンセプトを設定することです。単に宿泊施設や飲食店にするだけでなく、その地域ならではの体験や物語と結びつけることで、唯一無二の価値を生み出せます。第二に、ターゲットとする顧客層(特に訪日外国人観光客)のニーズを深く理解し、それに応じた快適性とサービスを提供することです。伝統的な雰囲気と現代的な利便性を両立させることが重要です。第三に、リノベーションには資金や専門知識が不可欠なため、地域の自治体、住民、そして古民家・町屋のリノベーションの専門知識を持つ建設業者等との連携が欠かせません。こうした多角的なパートナーシップが、プロジェクトを円滑に進め、持続可能な運営を可能にするのです。
Ⅰ.日本の古民家・町屋空き家問題の現状と地方創生への期待
ⅰ.空き家となった古民家・町屋の現状
日本において、空き家問題は社会全体の喫緊の課題として認識されています。総務省が発表する「住宅・土地統計調査」によると、2023年時点で全国の空き家数は約900万戸に達し、総住宅数に占める空き家率は13.8%と過去最高を記録しました。この数字は今後も増加の一途を辿ると予測されており、特に人口減少と高齢化が著しい地方部では、その傾向が顕著です。
空き家が発生する主な要因は多岐にわたります。少子高齢化とそれに伴う人口減少、核家族化の進展による世帯構成の変化は、親から子へと住まいが受け継がれないケースを増やしています。また、相続時の問題も深刻です。複数の相続人が存在する場合や、遠方に住む相続人が管理を放棄してしまうケース、あるいは相続したものの活用方法が見つからずに放置されるケースも少なくありません。さらに、耐震性の不安や老朽化による維持管理費の負担、既存住宅の質の課題なども、空き家が増える要因となっています。
これらの空き家、特に歴史的価値を持つ町屋や古民家が放置されることは、地域にさまざまな負の影響をもたらします。まず、老朽化が進んだ空き家は景観の悪化を招き、地域の魅力を損ないます。適切な管理がなされないことで、不法投棄の温床となったり、倒壊の危険性、あるいは雑草の繁茂による害虫の発生など、防犯・防災、衛生面でのリスクが高まります。また、地域コミュニティにおける交流の場が失われ、まちの活力が低下する要因にもなりかねません。
ⅱ.歴史的建造物である古民家・町屋の持つ文化的・観光的価値
しかし、これらの古民家・町屋は、単なる負の遺産ではありません。むしろ、地域固有の歴史や文化を物語る貴重な「地域資源」であり、これらを再生・活用することは、地方創生における大きな可能性を秘めています。伝統的な建築様式や独特の空間は、現代建築にはない唯一無二の価値を持ち、新たな魅力として生まれ変わる潜在力を秘めています。
古民家・町屋のリノベーションは、単に建物を修繕するだけでなく、その空間を通じて新たな交流を生み出し、地域に活気を取り戻す手段となります。例えば、宿泊施設や飲食店、交流スペースとして活用することで、地域外からの訪問者を呼び込み、新たな経済活動を生み出すことができます。これにより、観光振興、移住・定住促進、地域の新たな雇用の創出といった多角的な効果が期待され、持続可能な地域社会の実現に向けた重要な鍵となるのです。
Ⅱ.古民家・町屋リノベーションによる地方創生成功事例:ケーススタディ
ここでは、具体的な取り組みと、それが地域にどのような影響を与え、特に訪日外国人観光客の誘致にどう貢献したか、そして関わった企業等に焦点を当てます。
ⅰ.事例1:分散型ホテルとしての古民家再生と地域一体型の取り組み
事例名:
NIPPONIA(ニッポニア)(開発:株式会社NOTEなど、各地で展開 例:兵庫県丹波篠山市、千葉県佐原市、香川県三豊市など)
<概要とコンセプト>
各地の古民家や歴史的建造物を改修し、その地域の歴史や文化を体験できる分散型ホテルとして再生しています。まち全体をホテルに見立て、地域資源を活用した滞在体験を提供。単なる宿泊施設にとどまらず、地域での飲食や体験コンテンツを提供することで、地域経済全体への波及効果を狙っています。
<経済効果>
宿泊客の増加による観光消費の拡大に加え、地域の飲食、物販、体験型アクティビティなど、地域経済への広範な波及効果を生んでいます。地域の魅力を深く伝えることで、高い顧客満足度とリピーターを増やし、特に欧米圏やアジア圏からの訪日外国人観光客に人気を博しています。 地域外からの雇用創出にも貢献しています。
| *地域資源の徹底活用 | :その土地ならではの歴史、文化、自然、食といった地域資源を最大限に引き出し、宿泊体験と結びつけることで、唯一無二の価値を創出。 |
| *分散型ホテルとしてのまちづくり | :宿泊施設が点在することで、宿泊客がまち全体を回遊し、地域内の様々な商店や施設を利用する機会が増加。 |
| *地域との連携と雇用創出 | :地域住民がサービスの担い手となっている施設もあり、地域との交流が生まれ、地域全体で観光客を「もてなす」体制を構築。 |
<関与企業等>
株式会社NOTEは、古民家再生の企画、設計、リーシングまで一貫して手掛けています。地方創生を目的とした持続可能なビジネスモデルを構築し、各地のDMO1や自治体とも連携しています。
 出典:NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町 ウェブサイト
出典:NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町 ウェブサイト
1 DMOは「観光地域づくり法人」の略で、Destination Management/Marketing Organization の頭文字を取ったもの。地域の観光資源を有効活用し、持続可能な観光地域づくりを推進する組織を指す。
ⅱ.事例2:古民家を拠点とした地域の食文化発信と観光交流施設
事例名:
Satoyama Jujo(里山十帖)(運営:株式会社自遊人、新潟県南魚沼市)
<概要とコンセプト>
古民家を改修し、宿泊施設、レストラン、温泉施設、ショップを併設した複合施設です。「日本で一番、おもてなしの自由な宿」 をコンセプトに、新潟の食文化、温泉、里山の自然体験を融合させた体験を提供。特に「食」に注力し、地元の食材を活かした料理が人気を博しています。
<経済効果>
観光客誘致による地域経済の活性化、地元食材の需要拡大、地域産品のブランド力向上に貢献しています。日本の里山風景と食文化に魅力を感じる欧米圏、特に欧州からの訪日外国人観光客に高い評価を得ており、リピーターも多いです。 雇用創出にも貢献しています。
| *明確なコンセプトと独自性 | :「食」を軸に、里山の自然と融合した唯一無二の体験を提供することで、高付加価値なサービスを実現。 |
| *徹底した品質管理とブランディング | :地域の食材を厳選し、料理やデザイン、サービス細部にまでこだわり、高級感と満足度を追求。 |
| *メディア戦略と情報発信 | :自社メディアを活用した情報発信や、国内外の旅行メディアとの連携により、ターゲット層への認知度を向上。 |
<関与企業等>
株式会社自遊人は、雑誌出版業から派生し、地域資源を活用した宿泊施設の企画・運営、地域プロデュースなどを手掛けています。地方創生ビジネスの先駆者として知られています。
 出典:里山十帖 ウェブサイト
出典:里山十帖 ウェブサイトⅲ.事例3:京都の町家をコンセプチュアルな宿へ再生
事例名:
Nazuna(なずな)(運営:株式会社Nazuna、京都市内を中心に展開 例:Nazuna 京都 御所、Nazuna 京都 椿通など)
<概要とコンセプト>
京都市内に点在する築100年以上の京町家を改修し、日本の伝統的な美意識や文化をテーマにしたコンセプトホテルとして再生しています。Nazunaの各宿では、客室ごとに和菓子や京都の自然美など、テーマを設けています。趣の異なる空間と体験を提供。プライベートな空間を重視した客室が特徴です。
<経済効果>
京都を訪れる国内外の観光客、特に日本の伝統文化や独特の美意識に興味を持つ訪日外国人観光客(富裕層、欧米、アジア圏など)を強く惹きつけています。 高価格帯の宿泊施設として、地域全体の観光消費額の向上に貢献。周辺の飲食店や土産物店への波及効果も期待できます。
| *高付加価値戦略とコンセプト設定 | :単なる宿泊ではなく、日本の文化や美意識を深く体験できる「物語」を提供することで、高い単価設定と顧客満足度を実現しています。 |
| *上質な空間デザインとサービス | :京町家の構造を活かしつつ、現代的な快適さと洗練されたデザインを融合させ、特別な滞在空間を創出しています。 |
| *ターゲットを絞ったマーケティング | :富裕層や文化体験重視の旅行者に向けて、SNSや国や属性に合わせた動画コンテンツによる効果的な情報発信を行っています。 |
<関与企業等>
株式会社Nazunaは、京町家の再生・運営に特化したベンチャー企業であり、独自のブランド戦略とコンセプトメイキングで京町家宿泊市場において存在感を示しています。

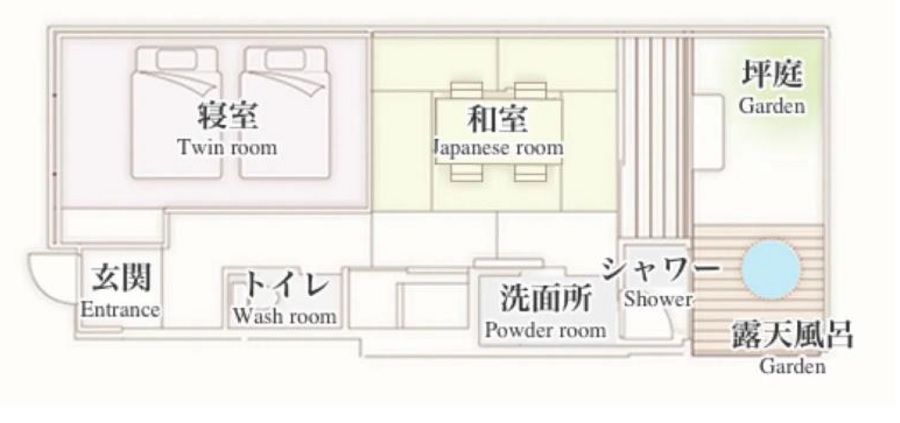 出典:NAZUNA ウェブサイト
出典:NAZUNA ウェブサイトⅢ.まとめ
古民家のリノベーションは、日本の多様な地方が持つ多様な歴史・文化的な魅力を現代に蘇らせ、地方創生とインバウンド誘致の強力な原動力となり得るものです。本レポートで分析した成功事例が示すように、古建築が持つ唯一無二の価値は、訪日外国人観光客に特別な体験を提供し、地域経済に大きな恩恵をもたらしています。彼らは単なる宿泊施設を求めるのではなく、その土地ならではの文化、歴史、そして人との交流を求めており、古民家・町屋はそのニーズにまさに合致しています。
古民家・町屋のリノベーションを成功させるポイントはいくつかあります。第一に、その建物が持つ歴史的・文化的価値を最大限に活かし、地域固有の魅力を引き出すコンセプトを設定することです。単に宿泊施設や飲食店にするだけでなく、その地域ならではの体験や物語と結びつけることで、さらなる価値を生み出せます。第二に、ターゲットとする顧客層(特に訪日外国人観光客)のニーズを深く理解し、それに応じた快適性とサービスを提供することです。伝統的な雰囲気と現代的な利便性を両立させることが重要です。第三に、リノベーションには資金や専門知識が不可欠なため、地域の自治体、住民、そして古民家・町屋のリノベーションの専門知識を持つ建設業者等との連携が欠かせません。こうした多角的なパートナーシップが、プロジェクトを円滑に進め、持続可能な運営を可能にするのです。
提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部
リサーチ課 米川 誠
本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。
企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから










