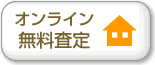一戸建ての場合、土地の境界を公図や登記簿で調べるだけでなく、念入りな調査が必要不可欠です。境界杭埋設の確認などをしっかり行うことで、購入していただいた後のトラブルも未然に防ぐことができて安心です。
境界に関するトラブルを予防するには、境界のあいまいさを解消することが一番。 万が一、登記上の情報と実測が違った場合、不動産の売買契約をする前に解決しておくことが肝心です。
一戸建てにつきものの境界線確認。
境界線トラブルに遭うことなく売買するには。
セカンドライフのための売却
豊かな自然に抱かれた住宅街の一角に建つ一戸建てに、二世帯で暮らしていたAさん。自分の結婚や長男の進学などのライフサイクルに合わせてリフォームをしてきましたが、玄関の暗さ、キッチンの孤立などの不満は解消できず、資金計画を練りながら、建て替えの機会を待っていました。
そんな折、ご主人のお父さんが定年後に再就職した会社を退職し、家を売って田舎の実家でのんびりと暮したいと希望。「資金の一部はAさんに援助(※1)するから、住まいは自分たちで探すように」と言うのです。
突然の展開にAさんはびっくり。今後の計画を立てるために夫婦で話し合い、自分たちはマンションを購入して両親の田舎暮らしの夢をかなえてあげようという結論を得ました。親思いのAさんらしく、住まいの売却活動を手伝うために早速、不動産会社を訪問。不動産の営業担当者は、仲介手数料など売却にかかる経費のアドバイスに加え、隣地との境界、道路との境界等の確認も必要だといいました。調査に時間がかかることが予測されたので、すぐに査定するよう依頼しました。
境界線トラブルを乗り越える
不動産会社は、役所や法務局での調査を行い、物件の外観や室内の状況なども確認。次に隣家も立ち会いのもとで土を掘り起こして境界杭を確認したところ、隣家よりも先に建築をしていたAさん宅の塀が10cm越境していることが判明。Aさんと両親は、これまで仲良く付き合ってきた隣家に迷惑をかけないよう、「買主が新築する際には越境しない」と話し合い、念書を交わして解決しました。その間に売却意思も固め、不動産会社に売却を依頼しました。築年数が経っているとはいえ、Aさん宅は、和風庭園を設け、木を活かした重厚な和風建築。建物の建った状態をイメージしやすいよう、家は取り壊さずに古家付きの土地として販売することに。
物件の魅力である現地周辺や駅前の写真などをホームページ上のデジタルオープンハウスで掲載し、立地のよさをアピールしました。掲載した翌日に、見学希望の方から連絡が入りました。購入候補の一つとしてAさんの物件を検討したい、と。
しかしながら1週間後に返事がきて、他の不動産会社で同じくらいの面積で予算の低い土地があって、そちらを購入されることになりました。
ところがしばらくして、断ってきた買主さんから「もう一度検討したい」と連絡が入りました。というのも、予定していた土地が、契約直前になって境界杭がないという問題が発生したそうです。土地の持ち主と隣家が塀の所有をめぐって話し合いをしても折り合いがつかないため、後々のことを考えて諦めたそうです。その知らせを聞いて、Aさんはガッツポーズ。「心おきなく物件探しができる」と、マンション購入に向けての第一歩を踏み出すことになりました。
境界線の重要性を熟知しているはずの不動産会社が、公図(登記所が保管している土地台帳付属地図)をうのみにし、境界確認を怠ると、売買契約後、訴訟問題に発展することもあります。紛争が起こる前から、事前の予防として対策を講じておく必要があります。Aさんのケースでは、不動産会社が調査の段階で、境界杭の確認をし、Aさんと隣家が話し合って解決してから販売したので、買主さんへの信頼も高まったといえるでしょう。
2008年7月制作
家族構成

- profile
- Aさん夫婦は共働きで、お子さんは社会人、ご両親はもうすぐ年金生活という大人ばかりの5人家族。物件は、Aさんが子どものときから住んでいる築40年の一戸建て。徒歩10分の最寄り駅から、快速を利用すれば都心まで乗り換えなしの30分強でアクセスでき、駅周辺には様々なショップがひしめく利便性のよい立地。
知っておきたい不動産用語
- 境界線
- 一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)を意味する登記上の土地の地番と地番の境目のこと。境界を示すために、石などでできた「境界杭」が境界に埋め込まれています。
- 贈与税について(※1)
- 親から住宅取得等資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば3500万円までは非課税になります。(相続時精算課税制度)
その他の不動産用語はこちら