- 国産豆のこと
- 世界の豆事情から見ると、日本は豆の消費量の多い国で、その大部分を占めるのは大豆です。豆腐や味噌、納豆など、加工食品としてのほうが馴染み深いかもしれません。産地は主に北海道で、大豆のほかにも、小豆やいんげん豆など、多くの豆は北海道で生産されています。国産豆は北海道産のほか、兵庫県丹波産の黒豆や岡山県産の稀少な白小豆などが有名です。食の安心・安全の面で、これら国産の豆を求める声が高まっています。
- 輸入豆のこと
- 国連食糧農業機関(FAO)は、いんげん豆、えんどう、そら豆、ガルバンゾ、レンズ豆の5種を世界で生産・流通している主な豆として挙げています。ひよこ豆の名で知られるガルバンゾは、インドなど菜食主義国で、重要なタンパク源とされており、ホクホクとした食感が、カレーやサラダに良く合います。また、レンズ豆はカメラのレンズに良く似た形が愛らしく、下ゆでせずすぐ煮えるのでスープとの相性抜群。その手軽さがさらに人気を呼んでいます。
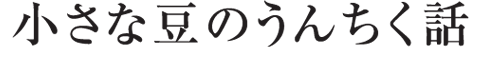
世界にはおよそ18000種類の豆が存在し、
そのうち70種類が食用として使用されています。
そして、落花生と大豆以外の豆を総称して、雑豆と呼び、
その用途の約60%が何と「あんこ」だというから驚きですね。
中でも、あずき、いんげん豆は
その約70%があんこ用として使用されています。
和菓子やあんぱん、おしるこなど、
日本ならではのおやつ文化を築いてきたのも「お豆さん」でした。

- 小豆
- 日本では約8割が北海道で生産されている、小豆。ポリフェノールの含有量が非常に多い。

- 大納言
- あずきの一種、大納言。その名の通り大粒で、煮崩れしにくい。甘納豆や鹿の子などの原料にされている。

- ささげ
- 小豆と同じく赤色の粒で、ササゲ属の仲間である。主産地は岡山県で知られ、小豆よりも若干粒が大きい。

- 金時豆
- 赤いんげん豆の代表、金時豆。主に、煮豆として食されており、北海道十勝地方の「大正金時」が有名。

- うずら豆
- うずら卵の殻のような模様からその名がついた、うずら豆。主に煮豆や甘納豆として食されている。

- 虎豆
- 白地でへそのまわりに斑紋がある、虎豆。煮豆用に最高とされ、「煮豆の王様」とも称される。

- 大福豆
- 白いんげん豆の高級品種、大福豆。真っ白で見た目も美しい。煮豆、豆きんとんなどで人気を誇る。

- 白花豆
- 大福豆より粒が大きく、真っ白な白花豆。主に甘納豆にして食されている。

- 紫花豆
- 「白花豆」と2つを併せて「花豆」とも呼ばれる、紫花豆。花が美しく、伝来当初は、観賞用として栽培されていた。

- 青えんどう
- 完熟前がグリーンピースで知られる、青えんどう。うぐいす餡のほか、スナック菓子の材料にも使用されている。

- 赤えんどう
- 色違いでこちらは赤色をした、赤えんどう。みつ豆や豆大福など、和菓子で馴染み深い。

- 黄大豆
- 普通大豆というと黄大豆のこと。たんぱく質を多く含む。北海道の鶴の子大豆は大粒で一級品として知られる。

- 黒大豆
- 大豆の仲間で黒豆として知られる黒大豆。黒豆の煮汁はのどによいとされる。丹波産のものが大粒で高級。

- 青大豆
- ひたし豆として知られる、青大豆。きなこの原料にも使用されている。主な産地は長野県や東北地方。


- 福井県若狭町にある「鳥浜貝塚」。数多くの縄文時代の遺物が出土した。
- 写真提供:若狭三方縄文博物館

- 鳥浜貝塚の約5800年前(縄文時代前期)の層より出土した豆の種子。左がケツルアズキ、右がリョクトウの種子が炭化したもの。
- 写真提供:福井県立若狭歴史民俗資料館
- 歴史の話
- 米、麦、あわ、きび、そして、豆。これら5種を併せて五穀といい、「五穀」には「重要な穀物」という意味があります。弥生時代以降、米は身分の高い人々に献上され、庶民はなかなか口にできるものではありませんでした。そのため栄養価の高い豆は、多くの人々にとって貴重な食料だったのです。そんな豆の歴史は古く、日本では縄文時代前期の遺跡から緑豆と思われる種子の炭化したものが出土しています。世界においても、大豆に関して言えば、中国の「詩経」(紀元前11~前6世紀頃)に、当時すでに黄河流域で食用として栽培されていたことが記されており、人類と豆とは相当長い付き合いであることが分かります。
- 日常使い・ハレ使い
- お祝いごとにひっぱりダコなのが、豆。その中でも、あずきやささげなど赤い豆には神秘的な力があるとされ、祝いの席にはこのような豆を使って、赤飯、赤粥をはじめ、ぼたもちやおはぎ、さくらもち、あんこ餅などのお供えをしながらみんなで楽しむものとして使われるようになりました。さらに、「まめ」という響きに「活動、力、元気、健やか」といった「まめやか」の意が込められており、1月14日の夜にその年の天候、穀物の収穫を豆を使って占う、「豆占い」、東北の盆踊歌、山陰地方の七夕の歌、各地の民話にと「豆」はいつも親しまれています。また、日常使いとしても、乾燥豆は季節を問わず出回っており、いつでも楽しめます。
- 健康の話
- ヘルシーブームが続く中、体に優しい「スローフード」として、豆の持つ優れた特性は多くの人が知るところとなりました。豆には、不足しがちなカルシウム、鉄分などのミネラル、ごぼうやさつまいもより多くの食物繊維、ビタミンB1などが含まれており、これらの働きによって、整腸作用や貧血を防ぎ、集中力を高めるなどの効果があるといわれています。そして、近年注目されているのが、大豆。大豆は「畑の肉」といわれるほど、良質なたんぱく質が豊富であることはご存知かと思いますが、さらに大豆の胚芽に含まれている「大豆イソフラボン」は女性ホルモンによく似た働きをするといわれています。ホルモンバランスの乱れが一因とされる、女性の更年期障害、骨粗しょう症、不眠症などの症状の緩和に作用するといわれています。現在、アメリカでも高タンパク低カロリーな「tofu」がブームを呼んでいます。そんな豆の力をうまく活用して健康維持に努めましょう。
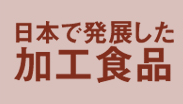
栄養価が高いとされる大豆。しかし、そのままたくさん食べると消化に悪いからと、 発酵させて食べるようになりました。大豆の加工食品は、納豆のほか、醤油や、味噌といった 和の味付けには欠かせない調味料の代表格として知られています。 大豆という一つの原料でこんな様々な加工食品があるのも日本ならではかもしれません。

- 味噌
- 味噌は、大豆に麦または米、麹、食塩水を混ぜて発酵させた食品です。味噌は昔、おかずとして食べるのが一般的でした。現在の「お味噌汁」のように、調味料として味噌が使われるようになったのは室町時代からだといわれています。

- 醤油
- 日本の醤油は大豆に小麦、麹、食塩水を混ぜて発酵させて作ります。醤油の始まりは、味噌を作るときに溜まった汁だともいわれています。江戸時代初期には高価だった醤油は、末期には次第に庶民の味として浸透し、日本の食卓に欠かせない調味料となりました。

- 納豆
- 納豆は蒸した大豆を納豆菌で発酵させたもの。常食すれば、酵素の働きで血栓症の防止効果も期待できます。ちなみに、奈良時代に中国から伝わったとされる納豆は、一見味噌のような糸を引かないものでした。今のような納豆が誕生したのは室町時代に入ってからのことだそうです。







