| (1) |
「残存価額」の廃止
平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について、現行の法定耐用年数経過時点の「残存価額」を撤廃し、法定耐用年数経過時点で全額(100%)が償却可能となります。
定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とします(250%定率法)。
|
| (2) |
「償却可能限度額」の廃止
償却可能限度額(取得価額の95%)を撤廃し、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとなります。
定率法を採用している場合、現行の定率法を続けても未償却残高は1円になりません。そこで、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、定率法を定額法に切り替えて減価償却費を計算することになります。
|
| (3) |
既存の減価償却資産の取り扱い
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(95%)まで償却した上で、翌事業年度以降5年間で均等償却ができることになります。改正法の施行後も、償却可能限度額に達するまでは、現行と同様の方法で償却を続けることになると思われます。
|
 |
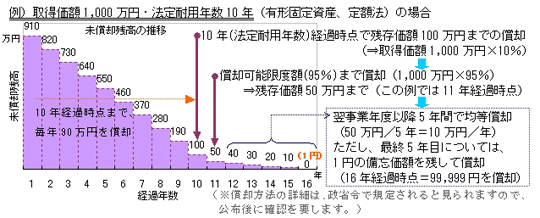 |
| (4) |
固定資産税の取り扱い
償却資産の固定資産税については、資産課税としての性格を踏まえ上記の償却方法の改正にか
かわらず、現行の評価方法が維持されることになります。
|