 |
従来、首都圏の人口動向といえば、首都圏に流入する人口を近郊で受け入れるという、いわゆる「都心のドーナツ化・郊外のベッドタウン化」で語られてきました。ところが今回の首都圏白書では、東京都心部で人口の増加傾向が強まる一方で、近郊整備地帯[「首都圏整備法」に規定する近郊整備地帯を指す。]の外縁部等の人口は減少傾向となっていることが報告されています。

|
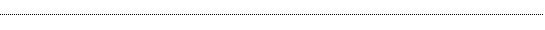 |
 |
|
とりわけ人口増加率が21.5%と高い伸びを示した都心3区(千代田区、中央区、港区)の都心3区における世帯主年齢別の転出入の状況(H10~15年)をみると、35~54歳の転入超過が大きく、65歳以上は転出超過となっていることがわかります。(図2参照)
|
 |
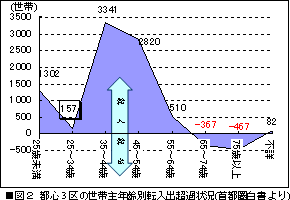 |
 |
|
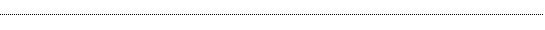 |
 |
近郊整備地帯においては、飯能市など人口減少傾向にある市区町村が見られますが、こちらは都心3区と逆に65歳以上は転入超過、65歳未満は転出超過となっており、今後更に高齢層の割合が高まることが想定されています。
|
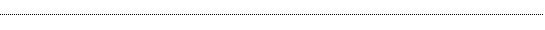 |
 |
人口減少市区町村の住宅の立地状況を見ると、最寄駅から2km以上の住宅数が33.8%、市街化区域以外が17.7%となっており、利便性の低い立地の住宅が比較的多いといえます。(その他の近郊整備地帯[人口減少市区町村以外]:最寄駅2km以上24%、市街化区域以外4.9%)
|
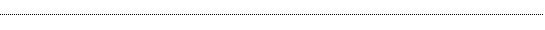 |
 |
H10⇒15年の人口減少市区町村における空き家率の推移を見ると、10.2%⇒11%と増加しており、さらに空き家の88.7%は市街化区域に立地し、利便性の高い住宅供給の阻害要因となっているようです。
|
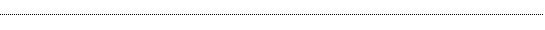 |
 |
H10⇒15年の人口減少市区町村における住宅供給数の増減割合をみると、増加率は低いものの5.6%増と一定量の住宅供給がなされています。市街化区域外においても住宅供給数が1.8%増加しており、既存宅地の空洞化と低密度な宅地の拡散が人口減少と平行して進行しているようです。
|
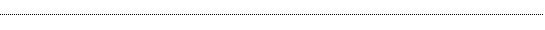 |
 |
これらを受けて、首都圏白書では「今後、首都圏郊外部の活力維持に向けては、まちなか居住の推進と市街地周辺部の低密度な開発の抑制を進める必要がある」としています。
|
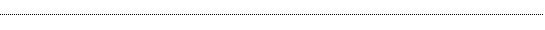 |